第1話 フォニックスについて
- Hiromi Holden
- 2022年4月21日
- 読了時間: 7分
本校は幼稚園生・小学生の授業にフォニックスを取り入れてます。
フォニックスとは何か?
今までの英語の教育方法とは違う方法なので
疑問に思う方も多いでしょう。
また、何故この時期にフォニックが必要なのか?
実際にどんな授業をするのか?などなど
これから徐々にシリーズ化して書いていこうと思います。
今日はフォニックスについて
どんなものなのかを説明しようと思います。
私たちは英語を中学高校で学びました。
今は小学生からですが・・・笑
中学の初めは必ずABCD・・・とアルファベットから習ったはず・・・。
ここは得意だった方多いでしょう。
私もそうです。笑
ここまで簡単だったにも関わらず
この得意だったアルファベットはすぐに姿を消し
いきなりTreeをツリーと読み
snakeをスネイクと読むように教えられる・・・。
どれも習ったアルファベットとは
かけ離れた発音で戸惑った方は多いのではないでしょうか。
一体、なんのためにアルファベットを勉強し
どこで、これは使われるのかと・・・・。
確かにアルファベットは記号や文字の名前として知ってないといけない。
でも、本当にただそれだけだった・・。
昔、高校で教えていたとき、英語が嫌いな生徒が
同じような理由をつけて
英語はわからないと言っていたことを思い出します・・。失笑
Treeはツリーと理由もなくツリーと読むと覚え
書くときは
「トゥレええ」と
無理にローマ字読みしながら覚える。笑
snakeはスネイクと最後にEがあるけどなんだろう?と思いつつも
スネイクと読むと理由もわからず覚え
書くときは 「スナケ」とローマ字読みしながら書き覚える・・。
多分、余程語学に優れた能力を持つ人以外は
ほとんどの場合こうやって覚えたはずではないでしょうか。。。
しかし、だんだん学年が上がるにつれてこのローマ字読みでは
どうしようもない単語に出会い始めます。。
例えばunfortunate(不運な)・・・見ただけで長く、
ローマ字読みするとどうしても最後のEを忘れてしまう。
ダメだ。。。長くて覚えられそうもない・・・
読むのも一苦労なのに書けなんて、本当に無理・・・。
ヤバイ・・英語難しい・・
という感じに段々と英語への「努力しようとする心」さえ削がれてしまう・・・。
これまでの
英語の単語には法則などはなく、そのまま覚えるべし・・・。
単語を覚えるには、理由ややり方は存在しないと思っていた人が
ほとんどでしょう。。
これをやり続けるには記憶力に頼る以外の方法はない。
もちろん、英語には音とは関係なくそのまま覚える言葉もある。
It や I などはその類です。
しかし、英語のほとんどの言葉は
その読み方に規則性があるのです。
つまり単語の読みの規則性を学ぶ・・・それがフォニックスなのです。
日本人が英語が苦手な理由の一つに
日本語を習得する上で
音読での学習方法に慣れてることが挙げられると思うのです。
「あ」は、「あ」と読むと習い
言葉の構造に「あ」が存在すれば
その部分を「あ」と読む。
他の言葉も同様に音を覚え
その音と音の組み合わせで、その単語の発音を覚え
意味を覚える・・・。
例; あ・お → あお → 青い色
英語にはこの学習方法は当てはまらない・・
今までの英語教育でそう感じていた人も多いことでしょう。
だからそのまま丸覚えしなきゃいけない
異次元の言語には苦手意識があった・・・。
しかし、実は英語も日本語と同じように音読で学習できるのです。
それがこのフォニックスという学習方法。
日本の音読による学習方法と同じように
音読の仕方を学んでいく。
ただ、日本語ほどシンプルなシステムではないので
そこはトレーニングが必要です・・・。
とりあえず
理解するのは実際に見てみるのが一番・・・ということで
今日はそのフォニックスがどのようなものか
いくつか例をあげていこうと思います。
例えば、先ほど例にあげた単語・・・Tree。
まあ、簡単な単語ですし
そのまま覚えられない単語ではないので
ほとんどの方はその法則を知らずとも書ける単語ではあります。
ただ、この単語はどうしてツリーと読むのかという理由を知っている人は
少ないかもですね。
フォニックスの法則でこの内訳を見ていきましょう。
T は トゥ のTの発音
R は ラ のRの発音
EE は イー と発音する。
T R EE
トゥ ラ イー
ラはRの部分だけなので
R+EEは リーに変換
子音Rと母音(アイウエオ)の組み合わせで読む、ローマ字と同じ法則の組み合わせ方法。
ラ Rあ
リ Rい(イーは「い」の発音)
ル Rう
レ Rえ
ロ Rお
これでトゥリーという発音になる。
他にEEの発音は
speed スピード feet フィート teeth ティース sneeze スニーズ
indeed インディード
前にある子音とくっついて音を変化させるが
基本全部EEはイー(いの段)の読み。
次に特殊なもの。snake。
この単語は英語の法則を知ることで解決できる。
Sはスの子音sの発音
Nはナの子音nの発音
次のakeは英語特有の a○eの発音。
AとEは真ん中に文字を挟むと
Aはエイと発音し
Eの音は消える。
a eに挟まれたKはクの子音Kの発音。
つまり
S N A K E
ス ナ エイ ク ❌
NとAを引っ付けると
N(子音)とエイのエ(母音)NE→ネ+イ=ネイとなる。
他には
cake ケイク whale ウェイル name ネイム cane ケイン
cape ケイプ tape テイプ mane メイン
何度も書くが、このa eの発音はAの部分がエイになりEは発音しない。
これもa eの a の前の子音とくっついて音が変化する。
a は「エイ」と発音するので「えの段」変換。ta○e → Tえイ→テイ
このようなルールを知っていれば
ムリにローマ字読みする事もなく
その学習方法から生まれる
日本語英語的な微妙な発音からも脱却できる。
さらに長い単語においては
分解して読む癖がつくため
読みも書きにも対応可能になる。
un for tu nate
アン フォ チュ ネイト
un アン(反対の意)
for フォー
tu テュ
nate ネイト
a e の法則でAはエイと発音Eは発音しない
aは前の子音nと引っ付いてネイト
しかし、この場合、最後のネイトは言いやすくするためネットと短く発音する。
アンフォーチュネット これが正しい読み
法則を知ると長い単語もそこまで難しくなく
なぜ最後にEがつくのかという理由もわかり書き忘れないし
単語の成り立ちを知ればさらに意味も深まる。
un + fortunate
反対 幸運な →「不幸な」
もちろん、フォニックスを知っていなくても英語は得意になれます。
努力と記憶力でなんとでもなるのは確か。
しかし、努力のみや記憶力のみに頼ると
余程語学に長けてる方以外は、
ほとんどの方が行き詰まりやすいです。
また、記憶力だけで英語の単語を覚えていると
下手したらテストが終わったらすぐに覚えた単語のほとんどを忘れ
簡単な単語さえ時が経つとスペルが思い出せない・・などの問題も出てきます。
まあ、毎日英語に触れてれば話は別ですが・・・。笑
フォニックスを知ってると
単語の成り立ちやその表記の音を知ることで
その単語を忘れてしまっても、読むことはできるので
その音で今まで覚えた記憶から
その単語の意味を予測できやすくなります。
逆に言えば
まる覚え方法は
その単語を忘れてしまった場合
読みかたがわからないから、読めず、
音がわからないので意味を思い出すきっかけが掴めず
意味もわからないし、もちろん書けない・・・となるわけです。
特に単語が長くなるとその傾向が強くなります。
多分、今書いてることは
多くの方が実際に感じることではないでしょうか・・・。
フォニックスは読めることで言える。
その言葉を聞いて意味を覚え・思い出せる。
その逆作業、言葉に発することで
音に合わせた文字が書け、単語や言葉を書ける。
つまり日本語と同じような学習方法で
英語の単語を習得できるシステムだから
日本でも浸透しやすい学習方法だと思うのです。
フォニックスを知ってるのと知らないのとでは
学習習得スピードに差が出るのは安易の予想がつくことでしょう。。
言葉(単語)の法則を知ることで
記憶力は最小限で多くの言葉にアクセスできる。
これがフォニックスの強みではないでしょうか。
イギリスから始まったこのフォニックスという学習方法は
今や、アメリカやその他の英語圏、世界のインターナショナルスクールでは
主流の英語学習方法です。
つまり、ネイティブの子供たちも
この方法で英語を学んでいます。
そして、B&H英会話もまた
世界と同じ基準で英語を習得する方法をとっています。
本校のフォニックスの授業では
英語の読みの法則を勉強し
読めて意味のわかる状態まで
授業でやっていきます。
次回はフォニックスと音について触れます・・
※わかりやすく説明するためにブログではカタカナ表記をしてますが
実際の授業では英語表記で音を覚えます。



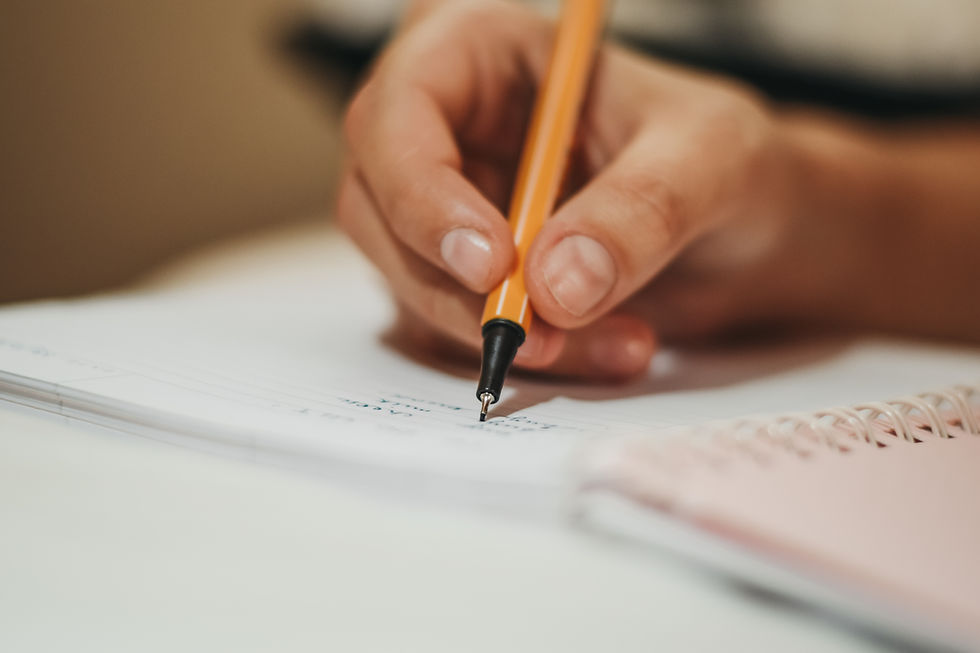
コメント